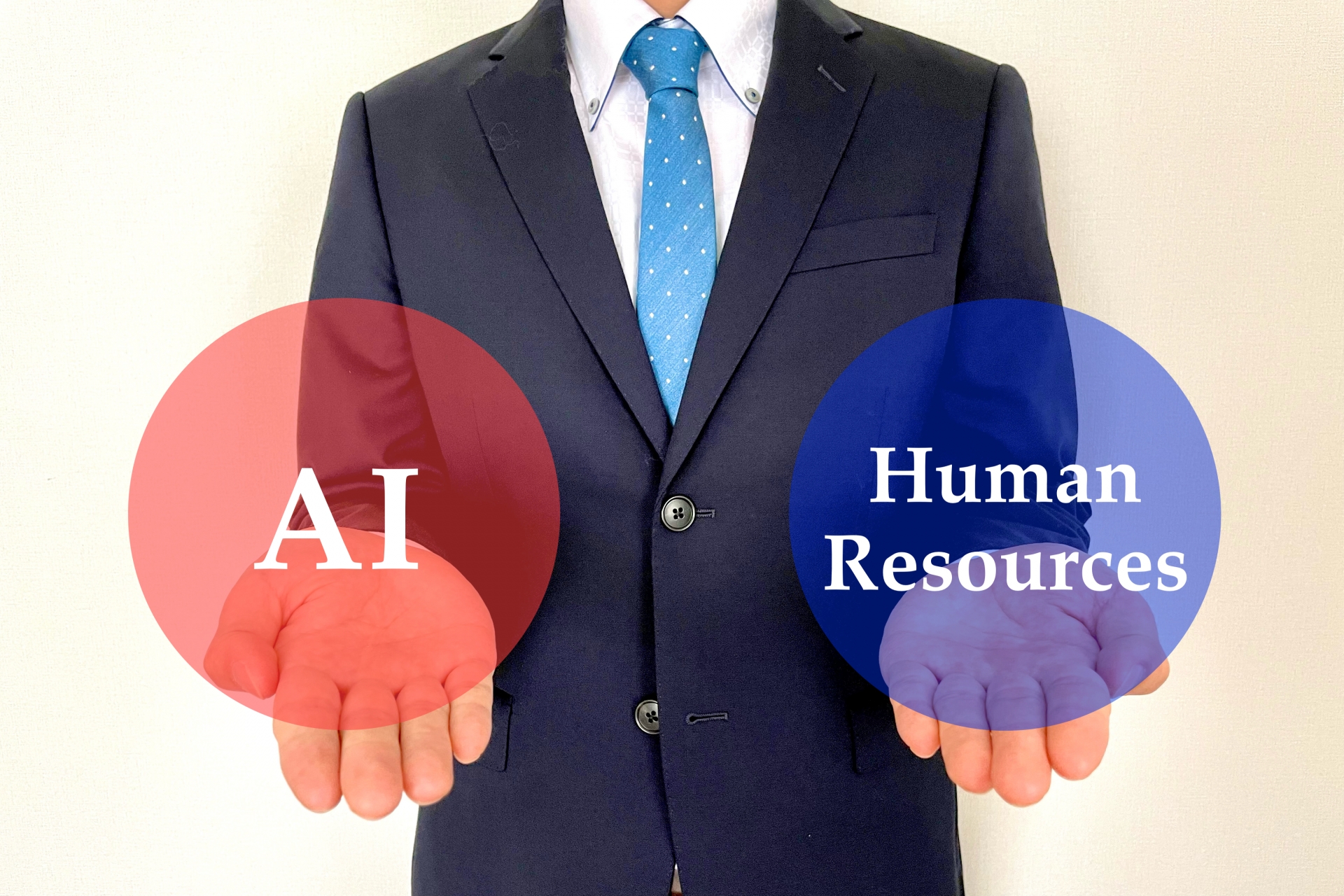
コラム
建設業の人材確保のポイント|人手不足の原因や対策方法を解説
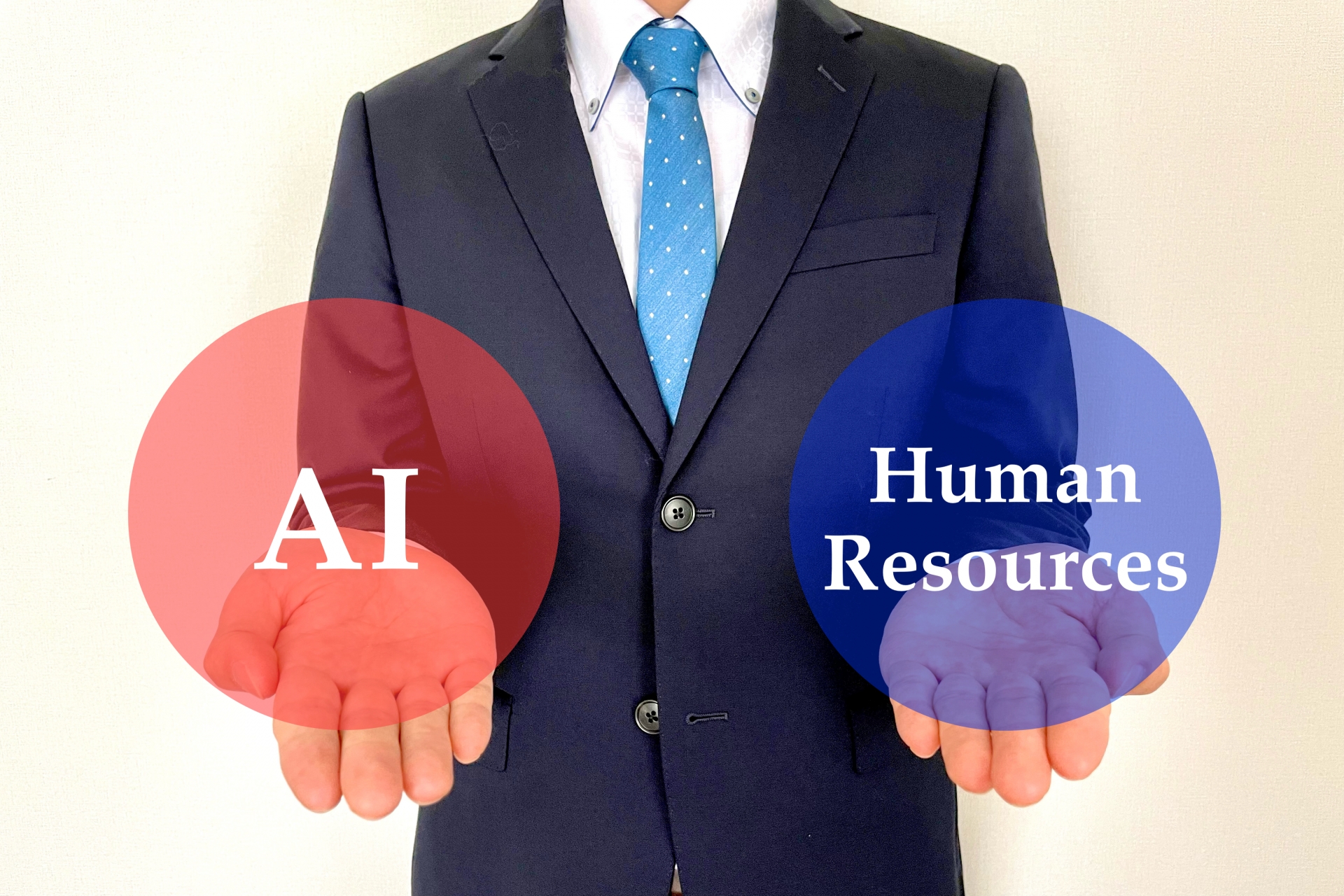
建設業界は深刻な人手不足に直面しています。需要が高まる一方で、働き手の確保が困難になっており、多くの企業が課題を抱えているのです。
本記事では、建設業の人材確保に重要な労働環境の改善やIT技術の導入、処遇の見直しなどを詳しく解説します。
建設業の人手が不足している原因とは

建設業界の人手不足は年々深刻化しており、その背景にはいくつかの要因があります。
国土交通省の調査によると、建設業就業者数は1997年の685万人から2021年には485万人まで減少しています。一方で建設需要は高まっており、働き手の確保が急務です。
人手不足の主な原因を詳しく見ていきましょう。
出典:国土交通省の調査「国土交通省の最近の建設業を巡る状況について」
高齢化が進んでいる
建設業界では働き手の高齢化が特に深刻な問題になっています。
2021年度の調査では、建設業就業者の55歳以上の割合が35.9%に達している一方、29歳以下の若年層はわずか12%にとどまっています。全産業の平均と比較すると、55歳以上の割合は31.5%、29歳以下は16.6%であることから、建設業界の高齢化がより進行していることがわかるでしょう。
今後10年間で多くのベテラン職人が定年退職を迎えるため、技術の継承と若手人材の確保が急務です。現在60歳以上の働き手が全体の4分の1を占めており、彼らが引退する前に後継者を育成する必要があります。
労働環境が悪く離職者が増えている
建設業界は他の産業と比べて離職率が高く、新卒者の離職率は48.5%に達しています。労働環境の問題が主な原因で、年間総実労働時間が全産業より340時間以上長いことが影響しています。「きつい、汚い、危険」の3Kイメージも根強く、若い世代が建設業を避ける要因です。
また、社会保険の未加入や適切な研修制度の不備、女性が働きやすい環境の不足なども離職につながっています。新入社員への十分なサポート体制がない企業では、入社後すぐに辞めてしまうケースが多く見られます。
労働条件の改善と職場環境の整備が人材定着の鍵といえるでしょう。
建設業の需要が増え供給が追いついていない
建設業界では需要の増加に対して働き手の供給が追いついていない状況が続いています。建設投資額は2014年から徐々に増加傾向にあり、2021年には約67兆円に達しています。
今後も大阪万博に向けたインフラ整備、リニア中央新幹線の建設、都市部のインフラ修繕など大規模な工事が予定されており、建設需要はさらに高まる見込みです。
一方で、働き手の確保が困難な状況が続いているため、企業間での人材獲得競争が激化しています。需要と供給のバランスが崩れているため、有能な人材を確保することがより困難になっており、業界全体で人材確保に向けた取り組みが必要です。
出典:建設投資の推移
円安で外国人労働者が減少している
外国人労働者の確保も困難になっており、円安の影響が大きく関わっています。これまで人手不足の解消に貢献してきた外国人労働者ですが、円安により日本で働くメリットが薄れているのが現状です。
日本における外国人建設技術者の賃金は月額20万円程度で推移している一方、外国人労働者の出身国として多いベトナムでは月額15万円程度まで上昇しています。ドル建て換算すると日本の賃金は著しく低下しており、わざわざ日本に来て働く理由が少なくなっています。
建設業の人材を確保する7つの方法

建設業界の人手不足を解決するためには、複数の対策を組み合わせて取り組むことが重要です。国土交通省では「労働者の処遇改善」「働き方改革の推進」「生産性の向上」を同時に進めることを推進しています。
ここでは、効果的な人材確保の方法を具体的に解説します。
労働者の処遇見直しと改善
建設業界で人材を確保するには、まず労働者の処遇改善が不可欠です。
給与水準の見直しはもちろん、社会保険への確実な加入、ボーナスや各種手当の充実が大切です。週休2日制の導入や有給休暇の取得促進により、働きやすい環境を整備することで、働き手の満足度を高められます。
福利厚生の充実も重要で、住宅手当や家族手当、育児支援制度などを設けることで、長期的に安心して働ける環境を作れます。安全衛生経費の適切な支払いや、危険作業に対する特別手当の支給も処遇改善につながるでしょう。
IT技術の導入検討
建設業界でのIT技術導入は、作業効率の向上と労働環境の改善に大きく貢献します。
BIMデータの活用により設計図作成の効率化を図り、クラウドサービスを使った書類管理で業務のスピードアップが可能です。ドローンを活用した測量作業により、危険な作業を軽減し、より正確なデータを取得できます。現場でのスマートフォンやタブレット活用により、リアルタイムでの情報共有と指示の伝達が可能。オンライン会議システムの導入で移動時間を削減し、効率的な打ち合わせが実現できます。
IT技術の導入により労働時間の短縮と安全性の向上を両立でき、若い世代にとって魅力的な職場環境を作れるでしょう。導入コストはかかりますが、長期的な生産性向上につながる投資として検討する価値があります。
行政の取り組みの活用
建設業の人材確保には、国や地方自治体が提供する支援制度の活用が効果的です。厚生労働省では建設事業主向けの助成金制度を設けており、主な制度には以下があります。
- トライアル雇用助成金:未経験者を試行的に雇用する際の支援
- 人材確保等支援助成金:働きやすい職場づくりに向けた取り組み支援
- 人材開発支援助成金:従業員の技能向上や研修に対する支援
これらの助成金を活用することで、採用や育成にかかるコストを軽減できます。
また、若年層や女性労働者を対象とした実習経費や賃金への助成率引き上げなどの制度もあります。派遣会社や人材紹介会社の中には、助成金活用のサポートを提供する企業もあるため、専門家のアドバイスを受けながら制度を有効活用することが重要です。
若手への研修や育成制度の充実
若手人材の確保と定着には、充実した研修制度と育成体制の構築が欠かせません。
入社時の基礎研修から始まり、段階的にスキルアップできるプログラムを用意することで、未経験者でも安心して働けます。メンターシッププログラムを設立し、経験豊富な職人が新入社員や若手従業員を指導する体制を作ることで、技術の継承と人材育成を同時に行うことが可能です。
建設技術、安全基準、プロジェクト管理などの専門知識を学べるトレーニングコースを設けることで、従業員のスキル向上と会社全体の生産性向上につながります。
資格取得の支援
建設業では多くの資格が必要で、資格取得支援制度の導入は人材確保と育成の両面で効果があります。会社が資格取得にかかる費用を全額または一部負担することで、従業員のスキルアップを促進できます。
対象となる資格は、施工管理技士、建築士、電気工事士、クレーン運転士など幅広い分野です。資格取得者に対する資格手当の支給により、従業員の学習意欲を高められます。社内で勉強会や講習会を開催し、資格取得に向けたサポート体制を整えることも重要です。
インターネットの活用
現代の人材確保には、インターネットを活用した情報発信と採用活動が不可欠です。多くの求職者がWebを通じて情報収集し、就職活動を行っているため、オンラインでの存在感を高めることが重要です。従来のハローワークや求人情報誌だけでなく、デジタル媒体を活用することで、より多くの求職者にアプローチできます。
ホームページ
自社ホームページは、会社の魅力を伝える重要なツールです。具体的な施工実績や会社の取り組み、先輩社員の声を掲載することで、求職者に安心感を与えられます。採用専用ページを設け、給与や福利厚生、研修制度などの詳細情報をわかりやすく紹介しましょう。
働く環境や現場の様子を写真や動画で紹介することで、建設業の魅力的な側面をアピールできます。ホームページから直接応募できるシステムを整えることで、応募のハードルを下げられます。SEO対策により検索での上位表示を目指し、より多くの人に見てもらえる工夫も必要です。
転職サイト
建設業に特化した転職サイトへの求人掲載は、効率的な人材確保につながります。
多くの求職者が転職サイトを利用しているため、自社の求人情報の露出機会を増やすことが可能です。転職サイトでは、職種や勤務地、給与などの条件で絞り込み検索ができるため、自社の条件に合った人材からの応募が期待できます。
また、複数の転職サイトに掲載することで、より幅広い層にアプローチできます。掲載内容は具体的で魅力的に書き、他社との差別化を図ることが重要です。転職サイトのスカウト機能を活用すれば、能動的に優秀な人材にアプローチできます。
SNS
SNSを活用した情報発信は、特に若い世代へのアプローチに効果的です。
Instagram、Facebook、XなどのSNSで、日常の現場作業や完成した建物、社員の様子を発信することで、建設業の魅力を伝えられます。3Kのネガティブなイメージを払拭し、建設業の社会貢献性ややりがいをアピールできるでしょう。また、ハッシュタグを活用することで、建設業に興味を持つ人に情報を届けやすくなります。
社員が自主的にSNSで会社の魅力を発信してくれるような、愛社精神の高い職場環境を作ることも重要です。動画コンテンツの活用により、よりわかりやすく魅力的な情報発信が可能になります。
女性労働者や外国人労働者の受け入れ
多様な働き手の受け入れは、人手不足解決の重要な方策です。
女性労働者の受け入れには、女性専用の更衣室やトイレの設置、育児休業制度やフレックスタイム制度の導入が必要です。検査工程など、女性が活躍しやすい業務を明確にし、きめ細かい作業を活かせる環境を整備しましょう。
外国人労働者については、特定技能制度を活用した受け入れが効果的です。2022年に外国人労働者の業務区分が19区から3区分に変更され、建設業にかかるすべての作業が新区分に分類されています。言語や文化の違いに対応するため、多言語対応のマニュアル作成や研修制度の充実が重要です。多様性のある職場は、オープンな雰囲気を生み出し、企業全体の魅力向上にもつながります。
建設業の人材を確保するためにかかるコスト

建設業での人材確保にはさまざまなコストが発生するため、事前に予算を把握しておくことが重要です。コストを正確に見積もることで、効率的な採用戦略を立てられます。
主なコストの内訳を詳しく見ていきましょう。
採用にかかる人件費
採用担当者は、求人の掲載、応募者との連絡調整、面接の実施、会社説明会の開催など、多岐にわたる業務を担います。優秀な人材を見極めるためには、建設業界に関する知識と採用の経験を持つ人材が望ましく、場合によっては外部から専門の採用担当者を雇用する必要もあるでしょう。
書類選考から最終面接に至るまで、応募者一人ひとりに対して複数時間の対応が必要で、応募者数が増えるほど人件費も膨らみます。また、面接官として経営陣や現場責任者が参加する場合は、その人件費も加味する必要があります。
採用活動の規模や期間に応じて、適切な人員体制と予算を計画することが重要です。
新人や若手への人件費
新たに従業員を採用する際は、基本給与に加えてさまざまな費用が発生します。
社会保険料(健康保険・厚生年金・雇用保険・労災保険)の会社負担分は、給与の約15%程度に上ります。また、作業に必要な安全装備品や工具、制服などの支給費用も必要です。
さらに、新入社員の場合は、仕事を覚えるまでの研修期間にも給料を支払う必要がありますが、その間は生産性があまり高くありません。
ほかにも、住宅手当や通勤手当、家族手当などがあれば、それも人件費に含まれます。ボーナスがある場合は、その分も年間の人件費として計算しなければなりません。
退職金制度がある会社では、将来の支給に備えて積立金を準備しておく必要があり、これも見逃せないコストのひとつです。
社内整備やIT導入にかかる費用
働きやすい環境を整備するためには、設備投資や制度整備に費用がかかります。
女性労働者の受け入れには、女性専用の更衣室やトイレの設置費用が必要です。安全管理の徹底には、最新の安全設備や保護具の購入費用がかかります。IT技術の導入では、ソフトウェアのライセンス料、タブレットやスマートフォンなどのハードウェア購入費、システム導入時の初期設定費用が発生します。
研修制度の充実には、外部講師への謝礼、研修施設の確保、教材の作成費用などが必要です。資格取得支援制度では、受験料や講習費用の会社負担分を予算化する必要があります。
これらの費用は初期投資として大きな金額になりますが、長期的な人材確保と生産性向上につながる重要な投資として捉えることが大切です。
まとめ
建設業界の人手不足は、高齢化の進行、労働環境の問題、円安による外国人労働者減少など複数の要因で発生しているのです。人材確保には処遇改善、IT導入、行政支援活用、研修制度充実が効果的でしょう。各企業が積極的に取り組むことで、業界全体の発展が期待できます。
