
コラム
建設業の人材育成における課題とは?課題解決法やポイントを学ぼう

建設業界は深刻な人手不足と技術継承の困難さに直面しています。従来の「背中を見て覚える」という指導方法では若手の早期離職が相次ぎ、ベテランの高度な技術やノウハウが確実に継承されない状況が続いています。
本記事では、建設業における人材育成の共通課題を明確にし、体系的な解決方法とポイントを詳しく解説します。
建設業における人材育成の5つの共通課題

建設業の人材育成には以下の5つの共通課題があります。
- 深刻な人手不足と高齢化による指導者不在
- 若手・新入社員の早期離職と定着率の低さ
- ベテランの高度な技術・ノウハウの継承問題
- 長時間労働の常態化と働き方改革の遅れ
- 育成ノウハウの不足と場当たり的なOJT
これらの課題は相互に関連し合っており、包括的な対策が必要です。
深刻な人手不足と高齢化による指導者不在
建設業界の就業者数は減少を続けており、ピーク時の平成9年と比較すると200万人以上減少しています。60歳以上の高齢労働者が全体の4分の1を占める一方、29歳以下の若年層は約12%にとどまっています。
高齢化が進むと、10年後には大量の熟練技術者が現場を離れる見込みです。指導できるベテラン社員が不足すれば、若手への技術伝達が困難になります。経験豊富な人材の退職により、現場での教育体制そのものが崩壊する危機に直面しているのです。
人手が足りない現場では、指導者自身が実務に追われ、育成に時間を割けません。結果として、若手は十分な教育を受けられず、技術習得が遅れます。
若手・新入社員の早期離職と定着率の低さ
建設業界では、入社後数年以内に退職する若手社員が少なくありません。早期離職の背景には、労働環境への不満や人間関係の問題、キャリアパスの不透明さがあります。
現場は閉鎖的な環境になりやすく、上司や先輩との相性が悪いと精神的な負担が大きくなります。丁寧な指導を受けられず放置されたと感じれば、成長実感が得られません。
若手社員は自己成長への関心が高く、将来の見通しが立たないと不安を抱きます。明確なキャリアプランや評価制度がない企業では、定着率の向上は望めません。早期離職が続けば、採用コストの増大と現場の負担増加という悪循環に陥ります。
ベテランの高度な技術・ノウハウの継承問題
建設現場では、長年の経験で培われた技術やノウハウが重要な資産です。しかし、経験則に基づく技能はマニュアル化が難しく、言語化されないまま属人的に保有されています。
「背中を見て覚えろ」という慣習が根強く残り、体系的な技術伝達の仕組みが整備されていません。ベテラン職人の「感覚」や「コツ」といった暗黙知は、実際に作業を見せながら伝える必要があります。
工期や納期に追われる現場では、ベテランが若手に技術を見せる余裕がありません。技術継承の機会が限られる中、熟練者の大量退職が迫っています。技術やノウハウが失われれば、品質低下や安全性の問題にもつながります。
長時間労働の常態化と働き方改革の遅れ
建設業の年間実労働時間は、全産業平均より340時間以上長い状況です。土曜日や祝日が休みでない現場が多く、年間出勤日数も他業種より16日多くなっています。
長時間労働が常態化している環境では、育成のための時間確保が困難です。若手社員は疲労が蓄積し、学習意欲が低下します。労働時間の長さは、建設業界への入職を避ける理由の一つになっています。
2024年から時間外労働の上限規制が適用され、働き方改革への対応が急務となりました。しかし、慣習的な働き方を変えるのは容易ではありません。業務効率化や工程管理の改善なしに労働時間を削減すれば、育成時間がさらに圧迫されます。
育成ノウハウの不足と場当たり的なOJT
建設業界では、体系的な人材育成制度が整備されていない企業が多く見られます。現場任せの教育では、指導者の能力や余裕によって教育の質にばらつきが生じます。
計画性のないOJTは、若手社員に何を学ぶべきか明確な指針を与えません。上司が忙しく十分な指導ができなければ、若手は放置されたと感じます。育成担当者自身も、どう教えればよいか分からず手探りの状態です。
育成プログラムやカリキュラムがないため、必要なスキルの習得が遅れます。評価基準も曖昧で、成長を実感しにくい環境です。場当たり的な指導では、組織全体の技術レベル向上は期待できません。
人材育成の課題を乗り越える!企業が得られる3つの大きなメリット

建設業における人材育成課題の解決は、企業に大きなメリットをもたらします。
- 生産性の向上と企業競争力の強化
- 従業員の定着率向上と採用力の強化
- 技術・ノウハウの確実な承継
これらのメリットを実現することで、企業の持続的な成長と発展が可能になります。
生産性の向上と企業競争力の強化
体系的な育成により、若手社員の技術習得スピードが向上します。早期に戦力化できれば、現場の生産性が高まります。熟練技術者の負担が軽減され、より高度な業務に集中できる環境が整います。
技術やノウハウが組織全体で共有されると、属人化が解消されます。標準化された作業手順により、品質の安定と工期短縮が実現します。デジタル技術を活用した育成を進めれば、業界全体で遅れているDX推進にもつながるでしょう。
人材が育つ企業は、難易度の高いプロジェクトも受注できます。技術力の向上は顧客からの信頼獲得につながり、競合他社との差別化要因となります。企業の成長と収益向上が期待できるのです。
従業員の定着率向上と採用力の強化
充実した育成制度は、従業員の満足度を高めます。成長実感を得られる環境では、若手社員のモチベーションが維持されます。キャリアパスが明確になれば、長期的な視点で働けます。
また、定着率が向上すると、採用コストの削減につながるのもメリットです。頻繁な人材補充が不要になり、育成投資の回収期間も確保できます。既存社員の経験蓄積により、組織全体のスキルレベルが底上げされます。
育成に力を入れる企業は、求職者からの評価も高まります。働きやすい職場として認知されれば、採用活動が有利に進みます。優秀な人材を獲得しやすくなり、企業の持続的な成長基盤が強化されるでしょう。
技術・ノウハウの確実な承継
計画的な育成により、ベテランの技術を次世代に引き継げます。マニュアル化や動画記録を活用すれば、暗黙知の可視化が進みます。複数の若手に技術を伝えることで、特定の個人に依存しない体制を構築できます。
また、技術継承が進むと、品質の維持と安全性の確保が可能です。長年培われた施工ノウハウや判断基準が失われるリスクを回避できます。企業の技術力という無形資産を守り、将来にわたって活用できるのです。
継承された技術は、さらなる改善や革新の基盤となります。若手が基礎を習得した上で新しいアイデアを加えれば、技術力の向上につながります。伝統と革新の両立が、企業の長期的な競争力を支えます。
建設業の人材育成課題を解決する5つの具体的な方法

建設業における人材育成課題の解決には、以下の5つの具体的な方法が効果的です。
- 体系的な研修制度(OJT・Off-JT)の構築
- 資格取得支援制度の導入とキャリアパスの明示
- メンター制度による精神的なサポート
- 人事評価制度の見直しと育成との連動
- ITツール・DXの活用による育成の効率化
これらの方法を組み合わせることで、包括的な育成環境を整備できます。
体系的な研修制度(OJT・Off-JT)の構築
現場での実務を通じて学ぶOJTと、座学や外部研修によるOff-JTを組み合わせた育成体制を整えます。OJTでは、経験豊富な先輩が実際の作業を見せながら指導します。若手は現場で起こる問題への対処法を学び、実践的なスキルを身につけることが可能です。
Off-JTでは、建設業の基礎知識や安全管理、図面の読み方などを体系的に教えます。外部の専門講師を招いた研修や、業界団体が提供する講習会への参加も効果的です。座学で理論を学んだ後、現場で実践することで理解が深まります。
定期的な勉強会の開催も有効です。週に1回、ベテラン社員が交代で講義を行えば、知識の共有が進みます。昼休み後の短時間学習など、日常業務に組み込める仕組みづくりが継続のポイントです。
資格取得支援制度の導入とキャリアパスの明示
施工管理技士や技術士などの資格取得を支援する制度を設けます。受験費用の補助や、勉強時間の確保、合格時の報奨金支給などが具体策です。資格取得により、従業員は専門性を高め、キャリアアップの道筋を描けます。
キャリアパスを明確に示すことで、将来のビジョンが見えやすくなります。入社後何年でどのような役職に就けるのか、必要な経験やスキルは何かを具体的に説明します。上司や先輩の実際のキャリアを例に示すと、イメージしやすくなります。
評価制度と連動させることで、努力が報われる仕組みを作ります。資格取得や技術習得が給与や昇進に反映されれば、モチベーションが維持されます。成長への道筋が見えることで、定着率の向上も期待できます。
メンター制度による精神的なサポート
新入社員や若手に対して、先輩社員がメンターとして付き添う制度を導入します。メンターは業務指導だけでなく、悩みの相談相手や精神的な支えとなります。閉鎖的になりがちな現場環境で、複数の人間関係を築くことが重要です。
直属の上司以外に相談できる相手がいると、問題の早期発見につながります。職場の人間関係で悩んだとき、第三者の視点でアドバイスを受けられます。定期的な面談を設定し、メンターが積極的にコミュニケーションを取る姿勢が大切です。
メンター自身の成長にもつながります。後輩を指導することで、自分の知識や経験を整理できます。教える過程で新たな気づきを得ることもあり、組織全体の学習効果が高まります。
人事評価制度の見直しと育成との連動
評価基準を明確にし、育成の進捗と連動させます。曖昧な評価では、従業員は何を目指せばよいか分かりません。技術習得の段階や業務遂行能力を具体的な指標で測定し、フィードバックします。
目標設定と評価を定期的に行い、成長を実感できる仕組みを作ります。半年や1年ごとに達成度を確認し、次の目標を設定します。評価結果を給与や昇進に反映させることで、努力が報われる実感を持てます。
評価面談では、強みと改善点を具体的に伝えます。一方的な評価ではなく、本人の意見や希望も聞きます。双方向のコミュニケーションにより、信頼関係が構築され、育成効果が高まります。
ITツール・DXの活用による育成の効率化
動画マニュアルやeラーニングシステムを活用し、いつでも学べる環境を整えます。ベテランの作業を撮影して共有すれば、技術の可視化が進みます。若者は繰り返し視聴でき、理解が深まります。
BIMやCADなどのデジタル技術の習得支援も重要です。実践的なトレーニングプログラムを用意し、段階的にスキルを高めます。デジタルツールを使いこなせる人材は、業務効率化や品質向上に貢献します。
オンライン会議システムを使った遠隔指導も効果的です。移動時間を削減し、複数の現場を効率的にサポートできます。デジタル技術の導入は、限られた時間の中で育成の質を高める手段となります。
人材育成の課題解決を成功させるための3つのポイント

建設業における人材育成の課題解決を成功させるためには、以下の3つのポイントが重要です。
- 経営層が本気でコミットする
- 中長期的な視点で計画的・継続的に行う
- 一人ひとりの価値観や目標に寄り添う
これらのポイントを押さえることで、効果的な人材育成の実現が可能になります。
経営層が本気でコミットする
人材育成を優先課題と位置づけ、経営層が積極的に関与します。予算配分や人員配置において、育成への投資を惜しまない姿勢を示します。トップのコミットメントがあると、現場も真剣に取り組みます。
経営層自身が育成の重要性を語り、従業員に伝えます。全社会議や朝礼で育成方針を説明し、理解を促します。経営者の言葉は組織文化の形成に大きな影響を与えます。
育成担当者を評価する仕組みも必要です。育成実績を人事考課に反映させれば、指導者のモチベーションが高まります。育成が評価される組織風土を作ることが成功の鍵です。
中長期的な視点で計画的・継続的に行う
短期的な成果を求めず、数年単位での育成計画を立てます。人材育成には時間がかかり、すぐに効果は表れません。焦らず継続することで、着実に成果が積み上がります。
年次ごとの目標を設定し、進捗を定期的に確認します。計画通りに進んでいない場合は、原因を分析して改善します。PDCAサイクルを回すことで、育成プログラムの質が向上します。
一時的な取り組みで終わらせず、組織に定着させることが重要です。担当者が変わっても継続できる仕組みを作ります。制度として確立することで、持続的な効果が得られます。
一人ひとりの価値観や目標に寄り添う
画一的な育成ではなく、個々の特性に合わせた指導を行います。若手社員の強みや関心を把握し、それを伸ばす方向で育成します。一律の方法では、個人の能力を最大限に引き出せません。
定期的な面談で、本人の希望やキャリア観を聞きます。目標設定は押し付けではなく、対話を通じて決めます。自分で設定した目標には、主体的に取り組む姿勢が生まれます。
多様な価値観を受け入れる柔軟性も必要です。従来の常識にとらわれず、新しい働き方や考え方を尊重します。個人を大切にする姿勢が、信頼関係と育成効果を生み出します。
建設業の人材育成に関するよくある質問
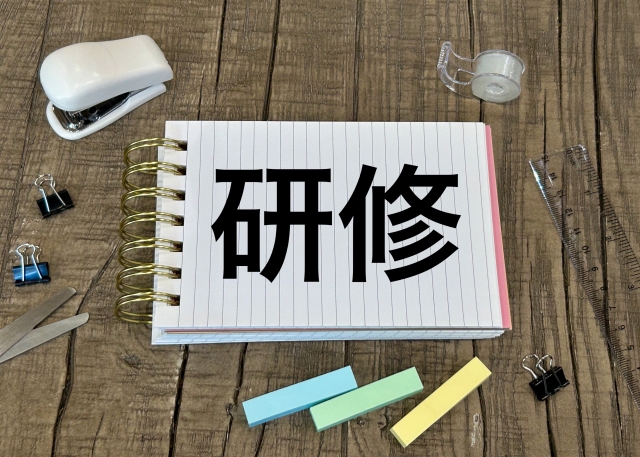
人材育成に取り組む中で、多くの企業が共通の悩みを抱えています。実務上の具体的な課題に対する解決策を知ることが重要です。
ここでは、建設業の人材育成に関してよく寄せられる3つの質問に回答します。
2024年問題による残業規制で、若手を指導する時間がますます取れません。どうすれば良いですか?
労働時間の制約がある中では、育成方法の効率化が必要です。まず、業務プロセスを見直し、無駄な作業を削減します。会議の時間短縮や書類作成の簡素化により、指導に充てる時間を確保します。
デジタルツールの活用も効果的です。動画マニュアルやeラーニングを用意すれば、若手は空き時間に自主学習できます。オンライン会議システムを使った遠隔指導により、移動時間を削減しながら複数の現場をサポートできます。
育成を特定の人に任せず、組織全体で分担します。複数の先輩が短時間ずつ指導すれば、個人の負担が軽減されます。昼休み後の15分間など、短時間の学習機会を日常業務に組み込む工夫も有効です。
ベテラン職人の「感覚」や「コツ」といった暗黙知を、どうすればマニュアル化して若手に継承できますか?
暗黙知の可視化には、まず作業を観察して言語化する作業が必要です。ベテランに作業手順を説明してもらい、重要なポイントを聞き取ります。なぜその判断をするのか、理由を明確にします。
作業の様子を動画で撮影し、解説を加えます。映像で見ることで、微妙な手の動きや力加減が伝わります。複数の角度から撮影すれば、より詳細に記録できます。
若手とベテランが一緒に作業しながら、対話を重ねることも大切です。実際にやってみせて、真似させて、確認するという手順を踏みます。質問しやすい雰囲気を作り、疑問点をその場で解消します。完璧なマニュアル化を目指すより、継続的に改善していく姿勢が重要です。
若手の現場監督が、年上の職人さんとうまくコミュニケーションを取れず、現場が円滑に進みません
若手監督には、まず基本的なコミュニケーションスキルを教えます。挨拶や報告・連絡・相談の徹底、敬意を持った言葉遣いなど、社会人としてのマナーが基礎です。年上の職人に対しては、経験を尊重する姿勢を示すことが重要です。
メンター制度を活用し、経験豊富な監督が同行してサポートします。実際のやり取りを見せることで、対応方法を学べます。定期的に面談を行い、困りごとを相談できる環境を整えます。
職人側にも、若手監督への協力を依頼します。全体会議で、次世代育成の重要性を説明します。若手の成長が現場全体の利益につながることを理解してもらいます。相互理解を深めることで、世代を超えた協力体制が構築されます。
まとめ
建設業の人材育成では、人手不足と高齢化、若手の早期離職、技術継承の困難さ、長時間労働、育成ノウハウの不足という5つの課題が存在します。解決には体系的な研修制度、資格取得支援、メンター制度、評価制度の見直し、デジタル技術活用が有効です。経営層のコミットメントと中長期的な視点で取り組むことが成功の鍵となります。
国土工営コンサルタンツでは、建設業の人材育成課題を解決する実践的なプログラムを提供しています。
定期的な学習機会の提供
毎週火曜日に1時間の勉強会を開催し、ベテラン社員がローテーションで図面の見方や施工管理など設計に関わる基本を講義形式で教えます。技術士の顧問講師による専門的な勉強会も数か月に一度実施し、構造力学などの大学レベルの内容や業務効率化についても学べます。
日常に組み込まれた学習習慣
昼休憩後の毎日15分間の自習時間を確保し、施工管理や技術士の試験勉強、最新技術の調査など、各自が必要な学習を行います。短時間でも継続することで、着実にスキルアップが図れます。
実践的なトレーニング
BIMCIMチームではAutoCADやRevitを使ったモデル作成、Navisworksでの施工ステップ作成、鉄筋の干渉チェック、CIVIL 3Dでの地形作成など、最新技術を実務で習得できます。構造物調査チームでは、Excelを使った点検調書の作成や数量計算、AutoCADやV-nasでの図面作成を学べます。
外国人社員向けの手厚いサポート
始業前の朝8時から先輩社員が日本語を教える時間を設け、テーマを設定し、レクリエーション形式で楽しく学習します。定期的に日本人社員が日本語トレーニングを行い、日本の文化や考え方も伝えます。内定者には入社前研修をオンラインで実施し、日本語や社会人マナー、土木の基礎知識を習得できます。
建設業の人材育成でお悩みの企業様は、ぜひ国土工営コンサルタンツにご相談ください。体系的な育成プログラムと実践的なトレーニングで、貴社の人材育成の課題解決をサポートします。
